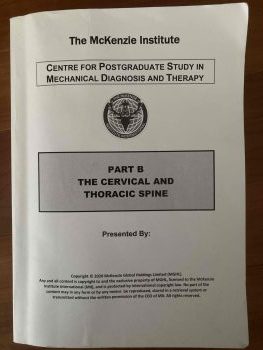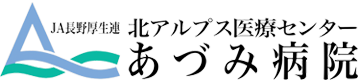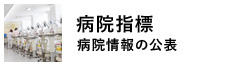スタッフブログ
「MDT」をご存知でしょうか?
度々こんにちは!あづみ病院で理学療法士として勤務しています龍崎です。
皆さんは「MDT」をご存知でしょうか?・・・とMDTの研修会についてご報告させていただいたのが昨年の6月でした。MDTの概略に関しては、2024.06.25の私の報告を参照して頂きたいと思います。
そこから少し込み入った話になりますが、MDTの組織はニュージーランドに本部があり、日本を含めた世界28ヵ国に支部を持ち、支部がない国であっても12ヵ国において教育講習会を行っています。すべての講習会(4日間のコースが4回と、2日間のコースが1回)を受講し、認定試験に合格すると、国際マッケンジー協会より認定資格が授与されます。大人になってから久々の試験を極度の緊張状態で頑張ってパスしたのが10年前。日々進歩する医療情勢の中で、MDTもアップデートされており、今回は「頸椎・胸椎に対するMDT」を再学習するために研修会へ参加してきました。
約200ページある教科書を使用した座学の他、実際の患者さんに講習会に参加していただき、評価からマネージメントまでを講師の先生が行う場面を見学したり、徒手的な技術の確認を行ったりと、研修会は相変わらずとても濃厚な4日間でした。認定資格者のため、受講生からの質問に答えたり、技術講習をサポートしたりと、自らが受講生の時とは違った緊張感も味わえました。
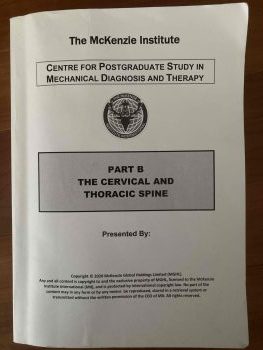
今回の研修会にて、アップデートできた知識として印象的だったのは、所謂「むち打ち症」に対するマネージメントが構築されていたことでした。斜頚や急性後弯を有していた場合の初期介入の原則など、日々の診療に活かせる知見を学ぶことが出来ました。
顎を前に突き出してこの画面を見ているそこのあなた!もしかしたら今抱えている首周りの症状は、MDTにて解決するかも?!是非、当院をチェックしてみてください!
指導医・研修医ブログ
初期研修医一年目の雑感
猛暑、というには大袈裟ではありますが、この暑さには些か参ってしまいますよね。太陽に冷えピタを貼りたいのですが、届かないので自分に貼って気を紛らわせています。
ご挨拶が遅れました。初期研修医一年目の大塚諒と申します。
気づけばあづみ病院に来てから5ヶ月が過ぎようとしています。1人しかいない同期、見知らぬ土地、大きすぎる駐車場に狭すぎる道など多方に不安を抱えていた4月の自分が可愛く思えるほど、現在はのらりくらりと過ごす日々を送らせてもらっています。
自己紹介も兼ねて少し自分の話をさせて頂きます。出身は東京の八王子というところで、昔は松任谷由美、今はローランドを排出した由緒正しき街です。道は広く山は低いためざっくりと言えば安曇野とは真逆の土地でした。所属した学校は全て関東圏内であったため、今回の入職を機に脱したこととなります。今まで縁のなかった安曇野、池田町に入職が決まった時、喜びと不安が同時に押し寄せたのを今でも覚えています。例えるならお盆に一瞬祖先が見えちゃった、そんなところです。
安曇野に来てよかったと思える点は、やはり北アルプスの景色でしょうか。職場に向かう際必ず視界に収まってくれるのですが、不思議と元気と意欲を与えてくれる有難い存在です。登山の趣味はなく、かといって海水浴もしない人間ですので、重力や浮力といった物理法則を到底意識しない生活を送っている自分です。これを良い機会にせめて重力だけでも体感しに登山に挑戦してみたいものです。
普段は何をしているのか、と問われても独り身ですのでスーパーに行くかちょっと背伸びしてスタバに行くかくらいなものです。この話を大学の後輩にしたら医者になる希望が失せたと言われてちょっぴり悲しかったです。
それにしてもツルヤは偉大ですね。これがない生活を覚えてないほど重宝させてもらっています。都心のスーパーとツルヤを比較したらガラケーとスマホくらい差があるというのが個人的見解です。

写真はツルヤの大きすぎる駐車場で開催されていたちょっとしたお祭りです。人が沢山いました。文章は適当ですが、業務は真面目に取り組んでおりますので心配しないでください。
指導医・研修医ブログ
初期研修が始まって4ヶ月が過ぎました。
4月から7月までは内科をローテートし、先生方から基本的な診察や対応についてご指導いただきました。
日々の業務の中で疑問が生じた際には、2年目の先輩方や専攻医の先生方に助けていただいています。
当直では、歩いて来院された患者さんの問診を担当しています。最初は基本的な「型」に沿って話を聞き、そこから徐々に個別の背景や訴えに踏み込むようにしています。当直帯の対応は、研修医である私にとっては毎回緊張の連続ですが、貴重な経験となっています。
現在、8月は小児科での研修を行っています。小児の回復力には日々驚かされ、同時にその健やかな回復に喜びも感じています。
小児の治療では、薬の種類や点滴量など、大人とは全く異なる考え方が求められることを学びました。薬の処方時には、薬剤部の方や上級医の先生に相談しながら慎重に対応しています。
それにしても、アンパンマンは今も変わらず子どもたちに大人気なんですね。

病院の近くに住んでいますが、夜になると春にはカエルの鳴き声が、そしてこの時期になると鈴虫の声が聞こえてきて、少しだけ秋の気配を感じています。
写真は、道の駅松川にて祖母と撮ったものです。
指導医・研修医ブログ
医局歓迎会
こんにちは。臨床研修管理委員会事務局です。
今回は先日行われた医局歓迎会(兼 暑気払い)の様子をお伝えします。
長らく自粛をしていた宴会の席ですが、今年度から徐々に開催しています。
今回は7月から整形外科へ入職された3名の先生方の歓迎会でした。美味しいお酒とお料理を楽しみながら談笑し大いに盛り上がりました!!


若手の先生方が入職してくださったことで、病院全体がさらに明るく活気づくと良いなと感じました。研修医も同世代の若手の先生方が診療する姿を間近で見ることで、研修や将来に対するモチベーションが上がればとても嬉しいです。

写真1 会場は町内のお洒落なイタリアンレストラン
写真2 雰囲気もバッチリです!!
写真3 見た目もキレイで、旬の夏野菜がたくさん入った美味しい料理でした。
指導医・研修医ブログ
研修医の様子~臨床研修管理委員会事務局~
こんにちは。臨床研修管理委員会事務局です。
これから時々、研修医や専攻医の先生たちのちょっとした日常を、医局の片隅からお届けしたいと思います。(先生たちが更新をさぼっているので( ;∀;))
今日は、研修医たちの自主的な勉強会の様子をご紹介します。

当院は自己研鑽の時間が比較的長く取られているため、研修医が自発的に学び合う雰囲気があります。
この勉強会は、2年目の先生たちが1年目の時に始めたもので、今では1年目も巻き込んで4人で続けています。

ちょっと距離感のある配置ですが・・・実際は和気あいあいとした空気が流れています。
研修医たちが互いに教え合い、刺激し合う姿を見ると、事務局としても嬉しくなります。
これからも彼らの成長を温かく見守っていきたいと思います。
スタッフブログ
「認定ハンドセラピスト」に認定されました。
このたび、一般社団法人日本ハンドセラピィ学会より「認定ハンドセラピスト」として認定を受けました。長野県では2人目の認定となります。「ハンドセラピィ」という言葉は、あまりなじみがないかもしれませんが、これは手指から肘にかけてのけがや病気に対して行う、専門的なリハビリテーションのことを指します。たとえば、骨折や腱・神経の損傷を受けた方に対して、関節の可動域を改善、筋力強化、繊細な手の動作の練習などを行います。また、必要に応じてオーダーメイドの装具を作製し、家事や仕事、スポーツなどへの復帰を支援します。

この資格を取得するにあたっては、研修会への参加や学会発表に加え、愛知県や北海道の病院での研修など、さまざまな学びの機会を経て、取得することができました。「日本ハンドセラピィ学会」は、毎年4月に「日本手外科学会」と共催で学術集会を開催しており、今年も整形外科医師4名とともに参加してまいりました。当院には、手外科専門医が2名在籍しており、手外科専門医2名と認定ハンドセラピストがそろう県内初の施設となりました。手や肘のことでお困りの際は、どうぞお気軽に「上肢再建外科センター」を受診ください。

上肢再建外科センター/リハビリテーション科 作業療法士 村井貴
スタッフブログ
放射線技師 スキルUP
2021年7月9日、厚生労働省医政局長より発出された「臨床放射線技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の交付について」に基づき、診療放射線技師の業務範囲が見直されました。これを受けて、厚生労働省が指定する告示研修が実施され、私も2025年6月15日に長野県看護協会会館にて開催された研修に参加してきました。

午前中は、ビデオ鑑賞を中心とした座学で、午後は実技に移りました。実技では、静脈路確保や、造影剤の投与に必要な動脈ラインの取り扱い、上部・下部消化管へのカテーテル挿入・抜去など、普段の業務ではあまり触れることのない技術をシミュレータやファントムを使って何度も練習しました。点滴ルートの確保は、やはり実際にやってみると難しく、手こずる場面もありましたが、繰り返し練習することで少しずつコツがつかめてきました。
放射線技師 A.F
スタッフブログ
手外科学会,ハンドセラピィ学会に参加して
2025年4月9日~10日に第68回日本手外科学会、10日~11日に第37回日本ハンドセラピィ学会に参加してきました。会場は横浜市のパシフィコ横浜で開催されました。
当院からは医師4名、作業療法士1名が参加してきました。
毎年4月に開催されるこの学会では、手外科医師や作業療法士が多く参加し、手と肘についての国内最大の学会になります。学会では10以上の会場で、シンポジウムや一般演題が同時進行で開催されており、どこに聞きにいくか迷ってしまうことも多いです。また会場も広く、職場の先生方に会うのも大変でした。
手外科学会では、上肢再建センターの中村医師が「重症手根管症候群患者における術後 1 年での母指球筋回復のMRI評価」という演題で発表を行いました。
ハンドセラピィ学会では私が「複数指のブシャール結節に対して掌側と背側アプローチによる人工関節置換術を施行した症例のスプリント療法」という演題で発表を行いました。同じような疾患や発表をされている方もいて、ディスカッションもできました。この経験をこれからの診療に役立てていきたいと思います。


上肢再建外科センター 作業療法士 村井貴
指導医・研修医ブログ
白馬診療所での研修~初期研修医~
初期研修医2年目の宮原尚也と申します。
10月後半から白馬診療所にて研修をさせていただいております。
自分自身の力不足を実感しながらも、学びの多い日々を過ごさせていただいています。
10月下旬から11月上旬にかけては観光シーズンということもあり外傷の患者さんが多い印象でしたが、11月中旬頃より感冒症状を訴える患者さんが増加し、インフルエンザやCOVID-19の方も増えてきております。
私自身生まれも育ちも長野県なので寒さ耐性があると自負しておりますが、流石に朝・夜の寒さは身に堪えます。自身の体調にも気を付けて研修をして参りたい所存です。
白馬診療所研修の大きな特徴として、自分の外来を持って患者さんをフォローすることができる点が挙げられます。
日当直の救急外来では、初療を担当し、必要であれば専門の先生へ引き継ぐことが多いですが、本研修では外来で対応可能な患者さんについては引き続き外来にて加療を行うことができます。
外傷処置や市中肺炎の治療、高血圧症などの生活習慣病のフォローなど、長期間の外来研修だからこそ経験できる症例が多数ありました。
また、限られた時間の中でポイントを絞って必要な診察を行い、鑑別を挙げ検査、治療に繋げていくことの難しさを日々痛感しております。ある程度の裁量を持って診療ができる環境ですので、1日の診療を振り返って、ここはこうするべきだったかもしれないと反省することも多々ありますが、少しずつでも前進していければと考えています。
皆様方の多大なるご支援により充実した研修をすることができました。本当に楽しく充実した日々でしたので、あっという間に過ぎ去ってしまい名残惜しく感じています。
お忙しい中ご指導いただいた先生方、看護師の皆様方、PT・OTの皆様方、事務の皆様方にこの場をお借りして心より感謝申し上げます。


写真1:宿舎近くから撮影した夜の景色です。白馬村の夜はとても寒いですが、その分空気が澄んでいて星空が大変綺麗でした。
写真2:白馬駅を中心に食事処が数多くあり、美味しいお店ばかりでした。気候は寒いですが、人の温かみがある場所です。研修期間中はシーズンではありませんでしたが、次はスキーをしに訪れようと思います。
スタッフブログ
~雪の季節、転倒注意です!~
作業療法士として白馬診療所に勤務しています西川です。
令和6年10月21日~11月17日の期間でWEB配信された、長野県南信地区ハンドセラピー勉強会特別研修会に参加しました。
WEB研修は、田舎在住でも受講しやすいことに加え、今回は繰り返し視聴が可能でしたので寝落ちしがちな私にはありがたかったです。
研修会テーマは「臨床で使えるハンドセラピーの知識~基礎から応用まで~」。整形外科における手や手指の手術後に必要となるリハビリテーションについてのお話でした。
同じ骨折の診断名でも、骨折部位や傷ついた周囲組織の状態などによって治療手法が変わってきます。また傷の修復に伴い生じる腱の癒着を予防することが大切になります。
研修を受けてあらためて早期リハビリテーションの重要性を感じました。
診療所のある白馬村は豪雪地帯。例年冬季になると、凍った歩道やスキー場で転んで骨折したり、自家用の除雪機で手指を怪我したりしてあづみ病院で手術を受け、その後診療所にリハビリテーション通院するという方々がいらっしゃいます。
白馬村からあづみ病院のある池田町まで雪道を通院するのは大変ですので、白馬診療所でしっかりとしたハンドセラピーが提供できるように研鑽を積んでいきたいと思います。
何はともあれ皆さん、転倒しませんように! 私もスキーで派手に転ばないよう気をつけたいと思います。

スタッフブログ
~目の前で人が倒れた時、何ができますか?~
理学療法士としてあづみ病院にて勤務しています龍﨑です。
さて、表題の問いに対する私の答え…というか、その際にもっと自分にできることはないのかという選択肢を増やすために参加させていただいたのが、相澤病院ヤマサホールにて開催されました「第21回相澤ICLSコース」になります。BLSについては、院外にて陸上競技の救護活動に関わらせていただいていることもあり、医療従事者としても一定の水準を満たしている自負はあります。そのBLSよりさらに一歩踏み込んだ技術と知識を学ぶことができるのが、日本救急医学会が主催するICLSコースです。『ICLSとはImmediate Cardiac Life Supportの略で、医療従事者のための蘇生トレーニングコース。特に突然の心停止に対する最初の10分間の対応と適切なチーム蘇生を習得することを目標としたコースです(ICLSホームページより一部変更して抜粋)』
実際の研修会では、心停止に対する基本的な知識(致死性不整脈・心電図・薬剤・気管挿管・心停止の原因検索など)を一通り復習し、あとはみっちり4時間半、シナリオに基づいたトレーニングを行ないました。理学療法士である自分は実際に薬剤決定や気管挿管、パドルでの除細動に直接かかわることはありませんが、多職種がどのように考えて行動しているのかを理解することで、サポートできることが格段に増えるメリットがあると感じました。個人的には是非すべての医療従事者に経験して欲しいという思いです。
これを読んでいる病院勤務のそこのあなた!是非コースに参加してみてください!


受講証明書とバッジをいただきました。
フレッシュナースブログ
2024新人研修~最高な最期のあり方~
こんにちは!
10月になり、紅葉がきれいな季節になりました。
4月から働き始め、半年が経ち夜勤業務が始まっています。日々忙しく過ぎていき、責任の重さに耐えきれるか不安になる日もありますが、同期や優しい先輩方に沢山助けられて働くことができています。同期とご飯を食べに行ったり、温泉に行ったりしてリフレッシュしながら仕事とプライベートを両立できるように日々頑張っています!
10月の研修では、がん看護・緩和ケア・エンゼルケアについて学びました。
がん看護に欠かせないことと言えば、、、痛みを和らげるケアです。和らげるために医療麻薬を使用することがあります。痛みを緩和することができますが、その分リスクもたくさんあります。今回は、薬剤師さんに留意点などを教えていただき、医療麻薬を扱うときは慎重に扱わなければならないということを改めて感じました。

もし今、余命宣告をされたらあなたは何をしますか?
今回は、「もしバナゲーム」を新人4~5人に分かれて行いました。「もしバナゲーム」とは、亡くなる前に何を大切にしたいのかを考えるために、このカードを使用してグループのメンバーそれぞれの価値観を話し合いました。普段は踏み込みにくい考え方がゲームになることで抵抗なく話しやすくなると思いました!

エンゼルケア。それは死後のケアです。死に至った患者さんとその家族の別れの時に、その人らしく最期を迎えることができるように肌や唇の色、整容など整えて死後も患者さんの尊厳を保たれるよう行われます。そのためにも亡くなる前にどういう最期を迎えたいのか、家族と話しておくことが必要だと感じました。


今回の研修で、「人生の最期」のあり方について考えさせられました。
あたりまえの日常は恵まれていることだと感じ、最期はどのように大切にしていきたいか考え、家族や友人など大切な人にも伝えていきたいと思いました。
読者の皆さんも大切な人の理想の最期はどうのようにしたいか、これを機に話し合ってくださったら嬉しいです!
フレッシュナースブログ
~2024年 成長を感じた新人研修~
こんにちは。
今回のブログを担当します3階病棟新人看護師の安室です。
9月とはいえまだ夏を思わせる暑い日が続いていますが皆様お変わりなくお過ごしでしょうか?
私は安曇野に来て初めての秋を迎えようとしています。紅葉や秋のおいしい食べ物にわくわくして過ごしています。
今回の研修はこれまでの自分の中間評価から始まりました。
自分のできているところ、困っていることをそれぞれ振り返りグループ内で共有をしました。
振り返ると自分が入職して初めての頃よりも成長できていることに気づくことができました。同期の悩みや成長を知ることで自分も共に頑張っていこうと励みに繋がりました。

この写真ではKYT(危険予知トレーニング)についての研修をしています。お題となる写真を見ながら考えられる危険はなにか、どのように対策していくかをチームで話し合っている場面です。今回の研修から現場での具体的な対策について考えることができ、改めて危険を常に考えて行動することの重要性を学ぶことができました。また、チームで話し合うことで一人では気づくことができない危険を発見することができ危険に対する視野も広がりました。

次の写真は人工呼吸器について研修を受けている写真です。人工呼吸器は患者さんの生命維持に重要な機械です。
実際に機械に触って、使い方から設定値の見方まで把握することで、患者さんに安全に使用することができる準備をすることができました。


以上で私のブログは終わりになります。
看護師として働き始めて5か月が経ちましたがまだまだ学ぶことが多くあり、心強い先輩方に支えていただきながら少しずつ成長し一人前を目指して頑張っています。
忙しく大変な毎日ですが、「休むときは休む!」を大切にしながら働いていきたいと思います。ありがとうございました。
スタッフブログ
日本超音波医学会第97回学術集会に参加して
こんにちは。臨床検査科の龍﨑です。
認定超音波検査士の資格を取得して7年目になります。
5年ごとの認定超音波検査士の資格更新には、学会参加で得られる計50単位取得と、必修講習会の受講が必要となります。
今回、パシフィコ横浜で開催された、日本超音波医学会第97回学術集会に行って来ました。育児やコロナ禍でなかなか県外へも行けておらず、久々の遠出となりました。
医師による発表も多く、内容は難しいものも多かったですが、学会へ参加するためのフォーマルウェアに身を包んだ私を見て、「かか先生」と送り出してくれた子供達の姿を思い出しながら、日頃の睡眠不足に負けず、シンポジウムや必修講習会を受けてきました。
新しい心機能評価の指標や検査法を知り、最新の機器を見学し、興味深い書籍に出会ういい機会となりました。書籍は早速病院で購入していただきました。
慣れない格好、人混みに多少の疲労感はありましたが、家事から離れ、人が作ってくれた美味しいご飯を食べ、いつもの倍近くの睡眠をとり(家事がないと、こんなに寝れるんだ⁉︎)、リフレッシュにもなりました。
帰宅してすぐ、「かか先生」はいつもの「かか」に戻り、家事と育児に追われる日々です。たまには学会でリフレッシュもいいかもしれないですね。
今回の学会参加により、次回更新に必要な単位を取得できました。学会で得た知識をまた日々の業務に活かしていきたいと思います。

 ランチョンセセミナーのお弁当は横浜グランドインターコンチネンタルホテルのものでとてもおいしかったです。
ランチョンセセミナーのお弁当は横浜グランドインターコンチネンタルホテルのものでとてもおいしかったです。
スタッフブログ
第26回日本女性骨盤底医学会
女性骨盤底医学センター長の西澤名誉院長と、パシフィコ横浜で開催された第26回日本女性骨盤底医学会に参加してきました。
コロナ禍以降数年ぶりの参加となりましたが、県外他施設の理学療法士との情報交換をする機会もあり、講演以外にも有意義な学会となりました。
骨盤底筋トレーニングハンズオンセミナーでは、今まで経腹エコー下で骨盤底筋の収縮について評価をしていましたが、今回は初の試みとして経会陰エコーで行われたようです。
当院は経腹エコーで評価をしていますが、経会陰エコーの方がメリットも大きいと言われております。
今後、経会陰エコーを使ったハンズオンセミナーがありましたら、ぜひ参加し知識/技術を向上していきたいと思います。

理学療法士 佐々木