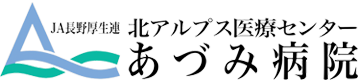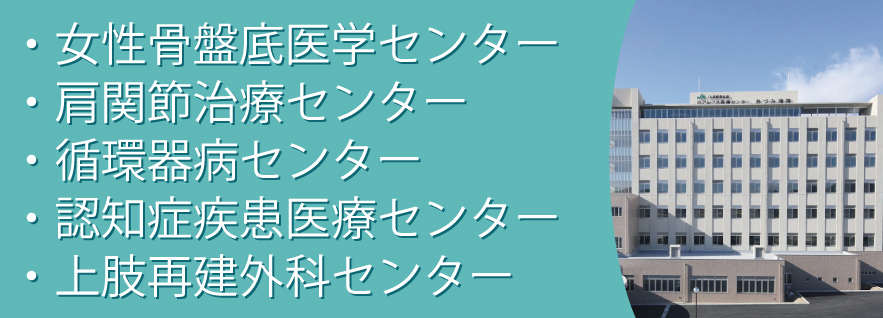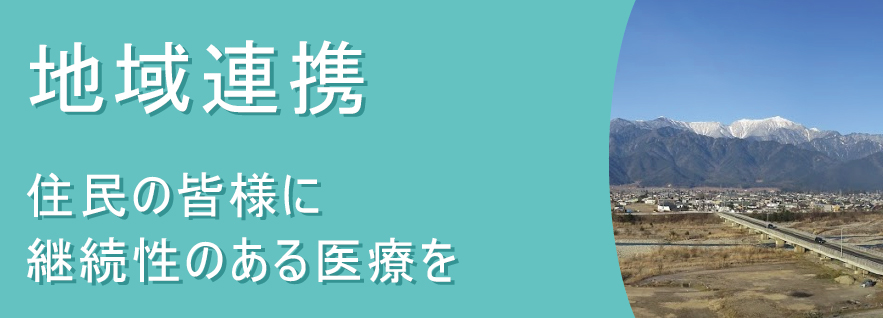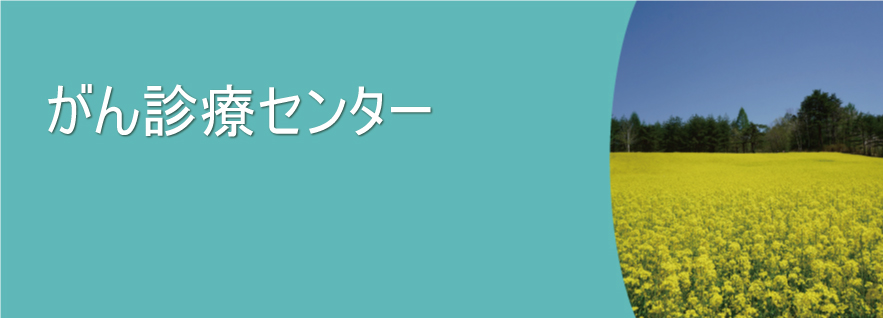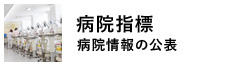リハビリテーション科
理念:地域の皆さまの、多様化したニーズに応じた適切で質の高いリハビリテーションを行います
基本方針
- 他部門、他職種との連携をはかりながらチーム医療に取り組みます
- 一人ひとりにあわせた、リハビリテーションを実施します
- 地域を含む包括的なリハビリテーションに取り組みます
- 知識・技術の研鑽に励み専門職としての責任を果たします
- 創造性と責任感をもつ人材育成に努めます
スタッフ構成
- 理学療法士(PT)39名(一般14名、肩関節治療センター16名、訪問4名、通所2名、白馬診療所3名)
- 作業療法士(OT)16名(身障8名、精神3名、訪問2名、精神訪問1名、通所1名、白馬診療所1名)
- 言語聴覚士(ST)3名(訪問兼務)
~認定資格等~
- 理学療法士、作業療法士臨床実習指導施設
- 3 学科合同呼吸療法認定士:理学療法士5名、作業療法士1名
- がんリハビリ研修終了者:理学療法士 13 名、作業療法士7名、言語聴党士2名
- 日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー:理学療法士1名
- 心臓リハビリテーション指導士:理学療法士3名
- 腎臓リハビリテーション指導士:理学療法士2名
- 認知症ケア専門士:言語聴覚士1名
- 認定理学療法士(循環)1名
- 専門理学療法士(運動器、スポーツ)1名
- 認定作業療法士2名
- 認定ハンドセラピスト1名
- リンパ浮腫療法士:理学療法士1名
- 地域包括ケア会議推進リーダー:理学療法士5名、言語聴覚士1名
- 介護予防推進リーダー:理学療法士5名、言語聴覚士1名
- 信州大学医学部 臨地実習委嘱講師
- 臨床実習指導者講習会終了者:理学療法士17名、作業療法士7名
- 介護福祉士:言語聴覚士1名
(2025年4月現在)理学療法(PT)部門
理学療法とは、事故や病気、スポーツ中の怪我などによって身体に障害を持った方や身体の機能が衰えた高齢者が「起き上がる」「座る」「立つ」「歩く」などの「基本的な日常生活動作」を回復できるよう行うリハビリテーションのことをいいます。
整形外科リハビリテーション
整形外科理学療法では、背中の痛み、肩・膝股関節といった「体を動かす」ことに関わる関節や筋肉などの怪我や病気で入院された患者さんに対し、入院・手術の直後から積極的にリハビリテーションを実施しています。
患者さんの状態に合わせて、痛みの軽減、関節の動きを良くする、筋力を高めるなどの機能回復、日常生活動作や歩行練習を行います。また、医師、看護師、医療ソーシャルワーカーなど他職種と常に連携をとり患者さん一人ひとりに適した安全で効果的なリハビリを実施し、できる限り早く安心して自宅に帰れるよう支援しています。
【リハビリ室での歩行練習】

【膝関節に対するリハビリテーション】
【主な対象疾患】整形外科理学療法では、年間延べ550名程の入院患者さんのリハビリテーションを実施しています。主な疾患は高齢者の骨折、人工股・膝関節、脊椎手術や関節鏡術後などになります。
外来リハビリテーション
外来理学療法では、整形外科医の診察のもと手術をせずにリハビリテーションを行う保存療法(腰痛症、肩関節周囲炎、変形性股・膝関節症、鵞足炎(がぞくえん)など)の患者さんや入院から自宅に退院した後の患者さんへリハビリテーションを提供しています。
外来でのリハビリテーションに加え、生活上の注意点や自主トレーニング指導なども積極的に行い患者さんに寄り添った治療が行えるよう支援していきます。内科・外科疾患リハビリテーション
脳のような神経の病気、肺、心臓、腎臓などの内臓の病気の患者さんに対して治療と並行して、退院に向けて早期よりリハビリテーションを行っています。運動療法、物理療法を用い、入院中の体力低下予防、退院してから必要な動作を練習します。患者さん個々の状態にあわせた運動や方法、道具等を選択します。また、再発予防や、獲得した機能維持に向けて外来、訪問、通所リハビリにて継続したリハビリテーションを行っています。外科手術を受けられる方には手術後の早期回復を促すために手術前後でリハビリテーションを行っています。手術前から手術に備えて身体づくりをし、手術後は早期からリハビリテーションを開始しスムーズに元の生活に戻れるようにサポートしていきます。
【対象疾患】脳血管疾患(脳梗塞等)、神経疾患(パーキンソン病等)、循環器疾患(心不全・心筋梗塞・狭心症等)、呼吸器疾患(肺炎・肺気腫等)、悪性腫瘍、外科手術前後、内視鏡治療後等幅広く対応しています。
【心臓リハビリの様子】

【呼吸リハビリの様子】
女性骨盤底医学センター

【超音波を使用し筋肉の動きを一緒に確認】
【主な対象疾患】骨盤臓器脱(膀胱脱、子宮脱、直腸脱)と尿失禁(腹圧性尿失禁、切迫性尿失禁)
これらの疾患は女性特有の疾患で、中年以降に多いですが出産後の若年尿失禁も対象となります。また、男性の頻尿や前立腺手術後の尿漏れ、便漏れも女性骨盤底医学センターで対応しています。女性では解剖学的な男女差による骨盤底の弱さが重要で、加齢・分娩・肥満などが主な原因です。骨盤底筋群が弱くなると十分に働きにくくなるため、骨盤臓器脱や尿漏れ、便漏れなどの症状が生じてしまいます。この分野のリハビリは、骨盤底筋を自分の意思で動かしたり、緩めたりすることで機能および症状の改善を図っていきます。目で見える場所ではないため、正確に筋肉が動いているかどうかは超音波などを使用しながら患者さんと一緒に確認しながら行っています。女性には女性スタッフが、男性には男性スタッフが個室で対応しています。2024年度診療別症例数 整形外科 1,012件 内科 897件 循環器内科 408件 外科 308件 がん 252件 泌尿器科 44件 合計 2,921件 スポーツ障害外来(肩関節治療センター内)
 医師:村上 成道(MD Sports Support 代表)
医師:村上 成道(MD Sports Support 代表)
運動や競技をしている方に起こる身体の問題は、外傷と障害の2つに分けられます。外傷は転倒や衝突などのアクシデントでおこる骨折や捻挫といったケガのことです。そのような外傷はギプスやテーピングでの固定や、必要であれば手術をして治療します。一方スポーツ障害とは、競技によって体の一部に過度な負担がかかったり、上手く全身を使えず他の部位に負担をかけてしまうことで痛みなどの症状を出すことです。このようなスポーツ障害の症状は、単に患部の安静や手術で解決することは難しく、体全体の使い方や患部以外の筋力、関節の動きなどを修正しない限り症状を繰り返すことがあります。スポーツ障害はいろいろな問題点の積み重ねで起こります。痛みを我慢して放置したままスポーツを継続してしまうことで大きな障害やケガにつながってしまう可能性もあります。スポーツ障害外来では、そのような状態になる前に痛みを軽減させたり、関節の動きをよくしたり、筋力をつけたり、全身のバランスを整えたりするなど、それぞれの問題点に対して理学療法士がリハビリしていきます。何か症状がおありの方は一度お問い合わせください。作業療法(OT)部門
当院は、身体領域(ハンドセラピィ含む)と精神領域で診療しています。「作業」とは 食べたり、入浴したり、家事をしたり、仕事をしたり、趣味をしたり、人の日常生活に関わるすべての諸活動を「作業」と呼んでいます。作業療法は病気やけがなどによって、身体やこころに障がいをもった人に対してその人らしい生活をとり戻していくために、様々な作業活動を用いて、治療や支援をしています。
身障領域


日常生活の自立や介助量軽減を目指します。家事動作(調理 掃除など)を行ない家庭での役割を継続出来るように支援します。高次脳機能や認知機能を評価し障がいの理解に努めます。医療ソーシャルワーカーや理学療法士と協力し退院前に家屋調査を行い、福祉用具の提案や生活様式を検討します。
ハンドセラピィ
ハンドセラピィとは、リハビリテーションの中でも手の外傷や疾患に対する専門分野です。指はそれぞれが独立して動き,また鋭い感覚機能があることで精密な動きが可能となります。1本の指の怪我でも大きな障害(手の使いにくさ)となってしまうことも稀ではありません。そのため術後の場合は早期からリハビリテーションを開始し、「機能の改善」と、「生活する手」の獲得を目標としています。手指の関節の動きを改善したり、指先で物をつまむ練習を行います。またスプリント(装具)の作製や、感覚の検査も行います。
【対象疾患】骨折・脱臼(肘、前腕、指)、突き指によるPIP関節掌側版剥離骨折・マレット指・靭帯損傷、屈筋腱断裂、伸筋腱断裂、ばね指、母指CM関節症、切断指、TFCC損傷、デュピュイトラン拘縮、テニス肘、ゴルフ肘、肘部管症候群、手根管症候群などスプリント(装具)療法


痛みのある関節や、靭帯損傷などによる不安定な関節を保護します。また硬い関節を矯正したり、指の動きを補助する場合もあります。
感覚検査
感覚の鈍い部分を検査します。神経損傷や手根管症候群、肘部管症候群の手術前後に行います。


2024年度疾患別症例数(入院・外来) 手外科 833件 外科 292件 循環器内科 264件 整形外科 210件 血液内科 198件 呼吸器内科 165件 総合内科 161件 消化器内科 149件 精神科 37件 内科 30件 呼吸器外科 8件 在宅支援科 3件 歯科口腔外科 1件 合計 2703件 精神領域
健康的な機能に働きかけ、その人らしくより良い日常生活、社会生活が送れるようにサポートしていきます。「生活にメリハリをつけたい」「人とうまく付き合えるようになりたい」「就学や就労など社会復帰の準備をしたい」などの悩みをお持ちの方はお気軽にご連絡ください。 そのほか、認知症患者に対応したリハビリテーションやアルコール依存症患者向けの外来 通院心理教育プログラムも実施しています。
【対象疾患】 うつ病、双極性感情障害、認知症、アルコール依存症、摂食障害、統合失調症などの精神疾患全般に対応





言語療法(ST)部門
当院の言語療法部門では、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によることばの障害、また高齢者を中心とした飲み込みの障害(摂食嚥下障害)などに対応しています。
脳梗塞や脳出血を発症された場合、損傷を受けた脳の場所によっては失語症といったことばの障害や、構音障害といった発音の障害を生じることがあります。ことばによるコミュニケーションに制限が生じると、ご自分の意思を伝えることや、考えを適切に伝えることなどが難しくなってしまいます。ことばは人間だけが持っている大切な機能です。その機能が改善できるよう言語療法にて支援していきます。
その他、ご高齢の方を中心とした飲み込みの障害にも対応しています。高齢になると「食べる時にむせる」「食べ物がのどに詰まる」といった、摂食嚥下障害がみられる場合があります。食べることは楽しみの一つですが、摂食嚥下障害によってうまく食べられなかったり、誤嚥性肺炎といった肺炎を生じやすくなったりします。ご高齢の方がおいしく、安全に食べられるよう、医師や看護師をはじめ、関連スタッフと連携しながら状態の把握や、機能の改善、食べやすい食事形態の提案などにあたらせていただいています。飲み込みの事でお困りの際はご相談いただければと思います。