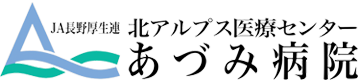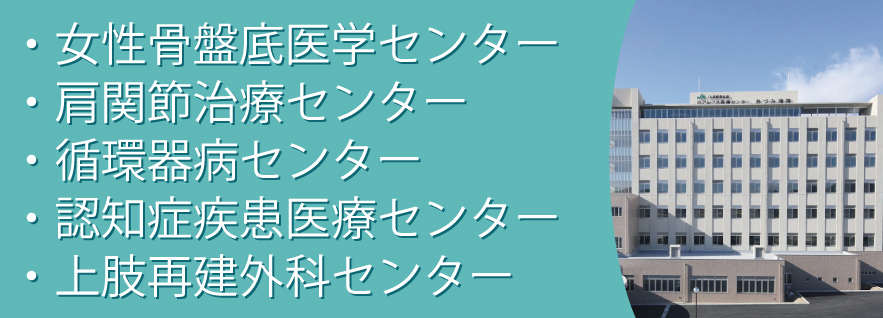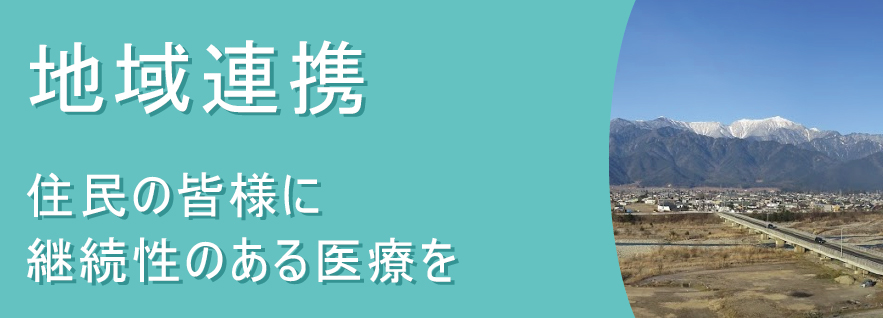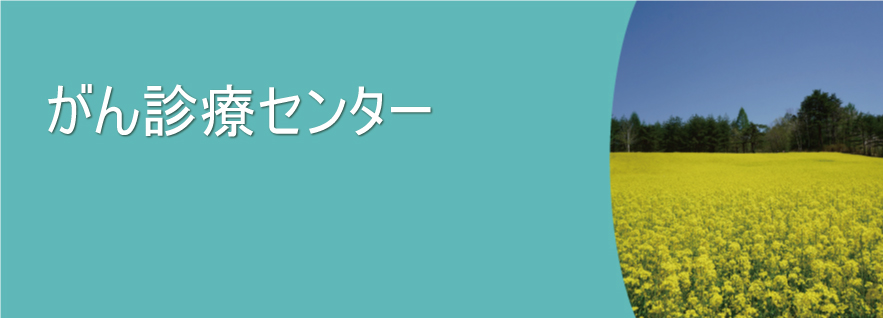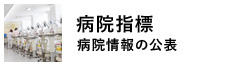認知症の勉強会
松本で地域の医師対象の認知症に関する講演会がありました。
「脳神経外科からみた認知症」、「精神科からみた認知症」、神経内科の教授の講演の三本立てでした。
脳神経外科からは手術で治療可能な正常圧水頭症や脳血管性認知症などの話がありました。

「精神科からみた認知症」は当院の村田志保先生が講演しました。
認知症診療において地域で多様な機能を果たしている認知症疾患センターの取り組みついて紹介し、豊富なデーターや実例を紹介しながら、中核症状が進行する時期にBPSDがでて、本人も家族もぎりぎりの状態となって精神科は関わることが多いけれども、より早くから診断し有効な介入ができないか、また終末期の看取り至るまで地域でトータルでどのようにみていけるかという問題提起をしました。
また、「診断した限りは最期まで付き合う覚悟が必要。」「認知症治療薬のやめ時についても議論が必要」、「認知症は定義からして社会的生活が困難になった状態、どこまで寄り添えるか」が問われていると訴えました。
神経内科の教授はアミロイド研究の歴史、FDG-PETによるイメージングの研究、認知症の病因論にせまる最新の知見と薬物治療の可能性についての話が主でした。
同じ認知症という疾患を相手にしていても科によってのスタンスの違いが見事に別れるものですね。
樋端Dr